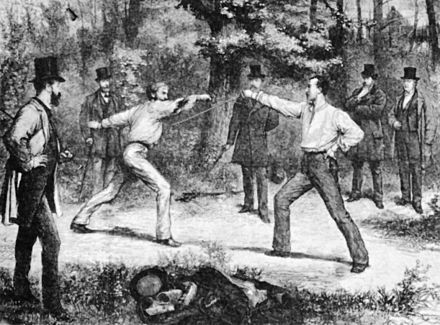「今と昔の暦がイキナリ1ヶ月ズレたのは給料1ヶ月分カットが目的」という驚き納得する話
POST DATE 2017.06.11
昔は「梅雨空け後の8月上旬頃」だった七夕

7月7日の七夕の夜、それは夜空で天の川をはさんで別れて浮かぶ織姫星(こと座ベガ)と彦星(わし座アルタイル)が1年に1度だけ逢える夜。…けれど、2人が久しぶりの再会を楽しむことができるのも「雨が降らなければ」の話。
実際のところ、7月7日はまだまだ雨が降り続く梅雨前線が日本を覆う真っ只中。1年に1度の大切な夜なのに、いくら何でも最悪のタイミング過ぎます。
けれど、本来の七夕は、梅雨が明けた8月上旬頃に行われていました。夜空に、織姫星(こと座ベガ)と彦星(わし座アルタイル)と白鳥座デネブが「夏の大三角形」として、美しく光り輝く頃です。なぜかというと、昔日本で使われていた旧暦(太陰太陽暦)は、今使われている新暦(太陽暦のグレゴリオ暦)と比べると、およそ1ヶ月遅れています。わかりやすく言うと、
・今(新暦)の1月は、昔(旧暦)の12月
・今(新暦)の2月が、昔(旧暦)の1月
…
・今(新暦)の7月が、昔(旧暦)の6月
・今(新暦)の8月が、昔(旧暦)の7月
というわけで、昔(旧暦)7月7日に行われていた七夕は、梅雨も明けた8月上旬の夏に行われていたわけです。同じように、アジア各国で祝われる「旧正月」が今の2月というのも、この新暦が旧暦より1月早い影響です。
旧暦の明治5年12月3日を、新暦の明治6年1月1日として切り替えた
旧暦から新暦への切り替えが日本で行われたのは、明治5年(1872年)の12月。その年の旧暦11月9日、旧暦から新暦への変更を宣言する「改暦詔書」が公布されます。その内容は、明治5年12月3日で旧暦の使用を止め、その日を新暦明治6年1月1日とする、というもの。年末近くの11月、まさかの「来年からは、全然違うカレンダー使うことにしました!」という明治政府の発表は、来年の暦(カレンダー)を作成真っ最中の業者など、大混乱を引き起こしたといいます。…「さまざまなことへの影響が大きい暦の変更を、なんでイキナリ急いでやるの?」と思ったアナタは鋭い!聞けば納得の理由があるのですが、それが明らかになるのはもう少し先。
なにはともあれ、明治5年の改暦で、旧暦12月3日(つまり旧暦の12月始め)を新暦1月1日(新暦の1月始まり)としたことにより、「新暦と旧暦がほぼ1ヶ月ズレる問題」が始まったのです。
「月の見え方」をもとに作られた旧暦(太陽太陰暦)は13番目の「閏月」がある
 日本がそれまで使っていた旧暦(太陽太陰暦)は、「お月さま」の見え方をもとにしたもの。繰り返される「お月さま」の見え方(満ち欠け)で「毎月」を作る。だから、毎月1日が「月が見えない」日で、毎月15日は満月の日。約29.5日で一回りするお月さまを基準として「毎月」を作ります。
日本がそれまで使っていた旧暦(太陽太陰暦)は、「お月さま」の見え方をもとにしたもの。繰り返される「お月さま」の見え方(満ち欠け)で「毎月」を作る。だから、毎月1日が「月が見えない」日で、毎月15日は満月の日。約29.5日で一回りするお月さまを基準として「毎月」を作ります。
けれど、月の満ち欠けの周期が約29.5日ということは、それぞれの月の日数は29日(小の月)か30日(大の月)ということになり、1年足し合わせてみても354日にしかならないのです。つまり新暦(太陽暦のグレゴリオ暦)とくらべると、11日も短い。3年たつと、旧暦の方は1ヶ月早く進んだ状態になってしまう。さらには、18年経つと、旧暦が(新暦より)6ヶ月進んだ状態、つまり夏と冬が入れ替わってしまうことになります!
というわけで、旧暦ではたまに「閏月」という「余計な1月」を入れることで、「月が進まない」ようにします。夏至や冬至、あるいは、春分や秋分といった大切な季節のタイミングが「一月ずれそうになったタイミング」で閏月を入れて、調整するのです。それが太陽太陰暦の仕組みです。
「明治6年の閏月分の給料1ヶ月分消し去るマジック」発動!
旧暦が持つ「13番目の月」、つまり閏月が重要なキーパーソン。この人物閏月がいなかったなたら、イキナリ突然の暦変更も起きず、新暦と旧暦の一月ズレ問題ももう少し小さなズレで済んだ可能性が高いのです。
実は、明治6年は閏月が予定されていた年でした。明治6年がもしも旧暦で存在していたら、つまり、太陽の動き(太陽暦)とのズレが大きくなり、1ヶ月近くになったズレをなくすために、「6月」の後にもう1回「閏6月」が入れる年だったのです。この明治6年の閏6月の登場が、犯人たちを「イキナリの暦変更」へと突き進ませます。
明治5年という時代、それは明治初期のインフレ・財政破綻の真っ最中。そんな中、前年の明治4年に、給料制度を江戸時代の年俸制から月給制に変更しました。そして、明治5年になって犯人たちは気付きます。「ヤバい!来年の明治6年は、13ヶ月あるじゃん!」「月給制にしちゃったら、12ヶ月分じゃなくて、13ヶ月分払わないとマズイじゃん!」「っていうか、月給制に去年しちゃったし、来年は閏月あるし!」・・・そして、犯人は考えた。
「そうだ!新暦に変更すればいいんだ!そうすれば閏月消えるじゃん!」
「時代はグローバル対応が必要とか言って、イキナリだけど変えちゃおう!」
・・・というわけで、明治5年12月のタイミングで、旧暦から新暦へのカレンダー変更がいきなり行われます。その犯人は、大蔵省というか明治初期の日本財政の責任者だった大隈重信。総理大臣になったり、早稲田大学を作ったりもするあの大隈重信。
財政破綻真っ只中の明治政府、明治政府にとっては素晴らしい(そして働く方にとってはとても残念な)「明治6年に払う給料を1ヶ月分消し去るマジック」すなわち「明治6年からの旧暦から新暦への変更」が行われたというわけです。
旧暦7月7日の七夕、それは織り姫と彦星が天の川を三日月の船で渡る日だった?

七夕の夜に浮かぶ上限の月は、下が丸くて上が平らな形から、「船」と例えられてきたりします。夏の上旬、空一番に輝く織り姫と彦星、天の川を上限の月に乗ってわたり、1年に1度だけの逢瀬を楽しむのが、昔ながらの旧暦の7月7日七夕です。
もし今年の新暦7月7日が雨だったとしても、8月上旬の旧暦7日の夜に、そんなことを考えつつ、夜空を見上げてみると面白いかも。
結論!
・新暦・旧暦の違いで、昔の行事は本当は約1ヶ月遅い季節に行われていた
・明治6年の13番目の月「閏月」がイキナリのカレンダー変更の原因だった!
・「1ヶ月ズレた」本当の理由は、明治政府が給料を1ヶ月分消したかったから!